<NO,53>(2008,3,17発行)
十勝開拓のパイオニア・・・依田勉三の苦闘の生涯
―「ケプロン報文」・札幌農学校フロンティアスピリッツに触発されて―
「晩成社」は、北海道の開拓を目的として明治15年(1882)1月、静岡県の伊豆大沢村(現在の松崎町)の豪農依田一族を中心に結成されました。中心となったのは、三男依田勉三と学友渡辺勝、鈴木銃太郎の三人でした。
依田勉三が北海道開拓の意志を固めたのは、慶応義塾に入学して福沢諭吉の薫陶を受けて開拓報国の念をいだくようになり、さらに「ケプロン報文」とクラーク博士の「札幌農学校」の新風の強い影響であったようです。勉三の明治14年・15年現地視察の後、「晩成社」移民団の一行13戸27名がオベリベリ(帯広村)に入植したのは明治16年(1883)5月のことでした。開墾は干ばつ、長雨、害虫などに見舞われて難渋をきわめるもので、多くの脱落者がでました。しかし勉三は、明治19年(1886)には大樹町に当縁(とうべり)牧場を開いて酪農に取り組み、さらに明治28年(1895)ころから水稲の試作を重ねて、幕別村に晩成社途別農場をスタートさせています。その後、明治35年(1902)にはバターなどの製造を開始、さらに3年後に練乳工場やサイロを構築、明治44年(1911)には缶詰工場も創業するなど、多くの苦難を乗り越えさまざまな事業に着手しています。しかし、いずれも事業としては実りのないままに、勉三は晩年中風に倒れ、大正14年(1925)12月12日、73歳の生涯を閉じます。いまは、帯広市共同墓地に眠っています。「晩成社」の事業としては、失敗の連続であったといわれます。しかし今日、依田勉三の苦闘は十勝農業のパイオニアとして高く評価されています。
今回は、この不退転の決意で、北海道十勝の開墾に生涯を捧げた「依田勉三」にスポットライトをあててみたいと思います。
■まえがき
蝦夷地(北海道)には、古くからのアイヌ民族の豊かな歴史と文化がありました。しかし、アイヌ民族は文字記録を持たないために、その歴史は、遺跡からの出土品や、アイヌの伝承、そして13世紀頃からの和人(シサム・シャモ、日本人)との交易の歴史などを通して、和人の視点から記述されたものから推定するだけで正確なところはわかりません。
江戸時代末期になって、近藤重蔵(1771~1829)の東蝦夷・択捉島の探検(1798年「大日本恵土呂布」の標柱を立てる)<1799年、幕府の東蝦夷地直轄化>や伊能忠敬(1745~1818)の蝦夷測量(1800)、続いて最上徳内(1754~1836)や富山元十郎などの千島列島探検 (1801年「天長地久大日本七属島」の標柱を立てる」などがありました。 <1802年、幕府、蝦夷奉行を置く、後に箱館奉行となる。>
その後、ロシアのニコライ・レザノフが日露通商を要求、続いてロシアの択捉島・樺太上陸による略奪、放火(フォボストツ事件)などがあり、幕府は警備を強化します。1807年、西蝦夷地を直轄化、箱館奉行を廃止して松前奉行を置きます。1808年、幕府が最上徳内(1754~1836)、松田伝十郎、間宮林蔵(1775~1844)を相次いで樺太に派遣します。(この時、松田伝十郎が樺太最西端ラッカ岬に「大日本国国境」の標柱を立てたといわれます。)
その後、ゴローニン捕捉事件(1821~1823)と高田屋嘉兵衛の活躍などがあり、日露関係の緩和を受け、幕府は蝦夷地を松前藩に返還。1854年日露和親条約締結、北海道は日本領、得撫島(ウルップ島)以北の千島列島がロシア領に決まりますが、樺太方面の国境は未確定でした。1865年岡本監輔が樺太最北端ガオト岬に至り「大日本領」と記した標柱を立てたといわれます。しかし、日露関係は緊張のまま新しい時代を迎えます。
明治元年(1868)1月の京都鳥羽伏見の戦いにはじまる戊辰戦争は、2月上野の彰義隊の戦い→8月会津戦争・飯森山白虎隊自刃→そして翌年5月の箱館戦争で終結します。明治2年(1869)7月、明治政府により開拓使が設置され、「北海道」と改称して新時代を迎えることになります。
明治政府は北海道開拓とロシアの南下に対する北方警備のため、移民政策をすすめます。屯田兵(有事には軍隊となる開拓民)の募集も開始し明治8年(1875)5月には、琴似屯田兵村に、仙台亘理藩・会津斗南藩・庄内藩士族の第1陣965人が入植しています。以後北海道には最終的に37の兵村ができ、合計約4万人が入植します。<明治37年(1904)屯田兵制度廃止>
明治10年(1877)以降、北海道移住の新しい流れの一つとして、失業士族対策の結社移民があります。明治12年(1879)、和歌山県士族岩橋徹輔の「開進社」による道南の乙部、長万部、岩内への入植。次いで明治13年(1880)、兵庫県士族鈴木清の「赤心社」による日高の西舎、荻伏への入植、さらに明治19年(1886)新潟県「北越植民社」の野幌入植などが続きます。ここでは、明治16年(1883)5月、十勝に入植した依田勉三の「晩成社」の苦闘の歴史をいろいろな資料を参考にご紹介したいと思います。
■依田勉三の生立ち
依田勉三は、ペリー来航の嘉永6年(1853)5月15日、伊豆国那賀郡大沢村(現在の松崎町)の豪農依田善右衛門の三男として生まれています。長男佐二平(二男は夭折)。三男勉三の幼名は久良之助。兄弟姉妹11人。依田家は、もと甲斐武田勝頼の重臣でしたが、天目山の戦いで織田軍に敗れた後、大沢の地に帰農したといわれます。
勉三は幼くして両親と死別し、7歳年長の兄佐二平に養育されます。漢学者の養伯父土屋宗三郎(三余)が開いていた「三余塾」で漢籍を学びます。<安政6年(1859)7歳のとき三余塾入門、久良之助から勉三に改名。> 幕末の伊豆は二宮尊徳の農本思想の影響が強く、この幼少時代から三余塾で、農本思想と開拓精神が勉三に植えつけられたものと思われます。明治5年(1872)8月、「謹申学舎」(塾長は元会津藩家老西郷頼母)に入塾。そこで、幕末の二宮尊徳が幕府から蝦夷地開拓の要請を受け、その門下生の大友亀太郎が開墾事業に活躍したことや函館戦争で官軍に敗れた榎本武揚の「蝦夷共和国」構想の話などを聞いて刺激を受けたといわれます。後、上京し、明治7年(1874)22歳のとき慶応義塾に入学して福沢諭吉の薫陶を受けます。福沢諭吉は独立自尊を説き、人口激増・食料不足を補うために北海道を大いに開拓すべきことも語ったようです。<また諭吉は、友人榎本武楊の助命嘆願にも努めています。> 勉三はしだいに開拓報国の念を強くし、明治8年(1875)すぐれた北海道開拓の全体構想を示した「ケプロン報文」(明治4年・明治6年・明治8年)「報文要略」(明治8年)に出会い、北海道開拓に生涯を賭ける決意を固めたといわれます。同年末、洋学勉強のため、英国人牧師ヒュー・ワッデル(1840~1901)の「ワッデル塾」で英語を学びます。そしてこの英学塾で、後の「晩成社」の3幹部となる依田勉三(24歳)・鈴木銃太郎(21歳)・渡辺勝(23歳)の出会いがあったようです。勉三はその後脚気と胃病のため中退して郷里に帰ります。
兄佐二平は、後に郡長、銀行頭取、汽船会社社長、国会議員などの要職を努めた人物ですが、この兄佐二平を手伝い洋学校の創設に尽力、明治12年(1879)1月15日に私立「豆陽学校」(現在の下田北高校)として開校、学校経営を助けます。佐二平が校長、渡辺勝を教頭として招き、勉三は教諭になります。この年4月、勉三26歳は義妹リク16歳と結婚します。勉三は教鞭をとるかたわら、開拓使次官後に長官となった黒田清隆が招聘したケプロンの視察報告書(730頁)を読んだり、新しい札幌農学校の様子を聞き及ぶにつけ、北海道開拓への思いに若き青春の血の沸き立つのを覚えたといわれます。
■晩成社の設立へ
勉三は明治14年(1881)8月17日 28歳、単身北海道へ渡り現地調査をしています。当時、北海道は石狩原野の開拓中心で、開拓使の役人は、札幌付近の苗穂村を推薦しています。しかし、勉三はこの申し出を断わり、十勝地方を中心にして道内各地を視察しています。そして伊豆に帰ると、十勝が将来性に富む土地であることを一族に力説し、明治15年(1882)1月、北海道での農場建設を目的とする「晩成社」(資本金5万円、今日の150億円に相当する大金)を設立したのです。兄佐ニ平社長、勉三副社長。社名は「大器晩成」に因み、開拓には長い時間がかかるが、必ず成功してみせるという願いをこめたものといわれます。渡辺勝と鈴木銃太郎は、ワッデル塾以来の親友で、のちに晩成社の3幹部として十勝の広野で共に活躍することになります。明治15年(1882)
5月、勉三は鈴木銃太郎と共に、再度、札幌県庁に土地貸し下げ手続きのため来道しています。 <当時の北海道は、明治15年2月開拓使廃止、札幌県・函舘県・根室県の三県となり、明治19年1月三県廃止、北海道庁設置。という状況>
開拓使時代から勉三の十勝開拓に協力した内田瀞技師(札幌農学校一期生)の骨折りなどで、十勝原野の中心部に「晩成社」入植の土地が決まったのでした。明治政府から未開地の無償払い下げを受け、今後15年間で一万町歩を開墾するという壮大な計画を立てています。7月16日、十勝川をさかのぼり帯広村に着き、開墾予定地を定めて、鈴木銃太郎は帯広に1人残り、勉三は伊豆へ帰国しています。当時の帯広はアイヌが10数戸約50人と和人が1戸あっただけといわれます。銃太郎はアイヌに助けられて豆や麦などを栽培して、一冬を越し、移民団の到着を待ちます。一方静岡では渡辺勝が移民募集をしていました。
■「晩成社」移民団の入植・開墾
明治16年(1883)4月9日、出発前日渡辺勝(29歳)と銃太郎妹鈴木カネ(25歳)との結婚式を勉三(30歳)・リク(20歳)夫妻の媒酌で行います。そして依田勉三(30歳)を団長とする「晩成社」移民団の一行13家族27名は、4月10日出発します。勉三・リクは2歳の俊介を義姉ふじに預けますが約半年後に夭折しています。一行は汽船「高砂丸」で横浜港を出港、4月14日函館に到着。その後陸海二手に分かれて帯広に向かいます。陸路隊は依田勉三隊長以下16人、海路隊は渡辺勝隊長以下11人で、それぞれ苦難の末、1ヶ月後の5月14日オベリベリ(わき水の流れる口の意・現在の帯広市)に着いています。全員が揃ったのは、5月20日でした。こうして、1年前から十勝に1人残って越冬していた鈴木銃太郎を含めて14戸、28人が最初の入植者となりました。「晩成社」移民団の中心となった勉三、銃太郎、勝・カネといった人たちは、当時の移民の中では数少ない高学歴のインテリでした。彼らは、入植後の苦闘の生活の中でも「ケプロン報告書を読む」「聖書を読む」「新聞を読む」という記述がその日記に、克明に書かれています。彼らは、なんと「ケプロン報文」や「聖書」を携えて入植した教養人でした。
明治16年(1883)、十勝開墾に入植した一行は、干ばつに加えて、野火、イナゴの大群、兎、鼠、鳥などの被害でほとんど収穫がなかったといわれます。この年10月17日に遅れて鈴木親長(53歳)・カネ親子、勉三の弟文三郎などが入地しています。親長・銃太郎・カネ、渡辺勝は洗礼を受けた熱心なクリスチャンでした。この信仰心が未開地入植の大きな精神的支柱になったようです。勝と結婚したカネは横浜の共立女学校(ミッションスクール)英学部を出た才媛で、入植後は、熱心に社員とアイヌの子供たちにも読み書きを教え、「十勝開拓の母」と称されたそうです。<教え子の山本金蔵が札幌農芸伝習所に学び、その時送った大豆数粒が、後の十勝一大生産物となる。>明治17年(1884)もまた絶望的な状況で、開墾は遅々として進まなかったといわれます。当時の帯広は奥地すぎて陸の孤島に等しく、勉三が大津(現在の豊頃町)に貯蔵してあった米の輸送も困難な状況でした。 <帯広~大津間の道路は、十勝集治監の囚人労働によって明治26年(1893)になってやっと開通しました> この飢餓の中で、勝が「落ちぶれた極度か豚とひとつ鍋」と詠んだのを、勉三が「開墾の始めは豚とひとつ鍋」と改めた歌は、今日も広く知られています。この間、多くの脱落者が出てたため、勉三は繰り返し開拓の精神訓話を試みたといわれます。妻リクは病気療養のため明治18年(1885) 9月 勉三に函館まで送られて伊豆に帰ります。翌明治19年(1886)帯広視察に来た依田佐二平に銃太郎が、晩成社改革を提言するも拒否されて、幹事を辞任しています。その後、銃太郎(31歳)はアイヌの酋長娘コカトアン(21歳・常盤と改名)と結婚して晩成社を去り、明治22年(1889)からシプチヤ(現在の芽室町)に定住、農場を開いて芽室町の草分けとなったといわれます。渡辺勝も明治26年(1893)から帯広を離れて、然別村(現在の音更町)に定住し、牧場経営をはじめています。

帯広神社前中島公園にある依田勉三の銅像 ( 2008年1月撮影:帯広百年記念館提供 )
■生花苗(おいかまない)の酪農経営
明治19年(1886)5月、このまま帯広にいては社業が不成功に終わることを心配し、勉三は弟の文三郎とともに、食料不足打開のため、帯広から約40キロ離れた当縁(とうべり)村生花苗(おいかまない)(現在の大樹町晩成)に牧場を開いて酪農に取り組みます。明治35年(1902)にはバターなどの製造をはじめ、3年後には練乳工場やサイロを建て、明治44年(1911)には缶詰工場も創業するなど、この牧場でさまざまな事業に自らの損失を忘れて着手しています。しかし、晩成社の経営としては上手くいかなかったようです。
この間に、明治20年(1887)には、弟文三郎が伊豆へ戻り翌年病没しています。そして明治22年(1889)に妻リクが4年間伊豆で療養して帯広に戻っています。明治25年(1892)頃には、ようやく状況も好転し食料も足りるようになり、小豆・大豆の収穫もめどがつくようになったといわれます。しかし、晩成社設立当初の15年で1万町歩を開墾しようという目標には遠く及ばず、10年かかって30町歩を開墾するのがやっとでした。同年(1892)11月、依田佐ニ平・勉三兄弟が緑綬褒章を授章したのを機に、奮起して晩成社の事業拡大を計画。明治27年(1894)函館に「丸成牛肉店」を開業して6年間滞在します。この年病気再発のリクと「愛ある」離婚、療養のため伊豆へ帰しています。その後世話する人があって、翌年函館生まれで二人の娘を持つ馬場サヨと再婚してます。勉三・サヨの間に千世という男子が生まれますが、わずか二ヶ月で病死、勉三は結局実子には恵まれていません。養子は数名いたようで、後に嫡子とした佐藤八百をキク(養女)と結婚させています。その後さらに、当別村に畜産会社を設立、帯広には木工場を作り然別村(現在の音更町)にも牧場を開いています。
■途別農場の稲作成功
このころ、勉三は、北限の地で水稲の試作を重ね、明治33年(1900)には幕別町途別(現在の幕別町)に「晩成社途別農場」をスタートさせています。明治37年(1904)には、冷害に強い黒毛品種「香(におい)早稲」を発見したのでした。そして、明治40年(1907)ころには30町歩の水田を作りますが、冷害・凶作が続いたため多くの小作人が去り残ったのは、勉三と2人の小作人だけになったといわれます。しかし勉三は決して希望を捨てず、大正4年(1915)からはサヨとともに途別の掘建小屋に住み込んで、排水溝・水路の改修、小作小屋の改築などの基盤整備に取り組みます。この時、実に5年がかりで約8キロメートルに及ぶ灌漑溝を完成させています。この地道な努力を続けて、少しずつ水田経営も軌道に乗るようになったのでした。しかし、晩成社の経営きびしく、大正5年(1916)には売買(うりかり)農場<帯広南東部>等を売却します。
大正9年(1920)11月に、勉三は途別農場の一応の成功を記念して祝宴を開いています。久しぶりに鈴木銃太郎や渡辺勝など晩成社同志12人が顔を合わせて、勉三の成功を心から祝ったといわれます。この時、勉三は68歳になっていました。苦難つづきの晩成社の開拓の歴史の中で、この日だけが勉三最良の日であったといわれます。しかし、至福の時は束の間で、勉三には晩成社の所有地売却など経営難の苦労が続きます。
■勉三倒れる
勉三は、大正13年(1924)、春より中風にかかります。9月16日、看病疲れで、サヨが先立ちます。その後リクが伊豆から来ますが、勉三と口論となり12月に再び伊豆に戻っています。<この年10月15日、兄佐ニ平没。>その後病勢は日ごとに悪化して、大正14年(1925)12月12日、十勝開拓45年に苦闘の生涯を捧げた依田勉三は、帯広町西2条9丁目の自宅で、「晩成社にはなにも残らん。しかし、十勝野には・・・」と語り静かに息を引きとったといわれます。享年73歳でした。リクは養子政雄を伴って葬儀に来て、嫡子八百夫妻の世話でそのまま広尾に住み約9年後の昭和10年(1935)11月3日、73歳の薄幸な生涯を閉じ、八百の手によって葬儀が行われたということです。<鈴木銃太郎は大正15年(1926)6月13日71歳没。渡辺勝は大正11年(1922)6月15日69歳没。カネは昭和20年(1945)12月1日83歳没。>
■「晩成社」十勝開拓の遺産
晩成社設立当初の15年間の開拓目標は、その後25年に延期され、借金も雪ダルマ式に増えて大正2年(1913)には当時のお金で負債額17万8千円に達したといわれます。さらに50年に引き延ばされても成功せず、昭和7年(1932)、創業50年満期となり莫大な負債をかかえて倒産同様に解散しています。晩成社員に残された土地も、出資者への配当もなく、勉三所有の土地も一坪もなく、すべて自作農への開放と借財の返済にあてられたのでした。しかし、勉三が、若き日、慶応義塾の福沢諭吉の薫陶を受け・ケプロン報文に出会って北海道開拓の決意を固めた「ますらをが心定めし北の海風吹かば吹け浪立たばたて」の決意は、入植以後約半世紀すこしも揺るがず、十勝開拓の先駆者として、開拓済民の使命感をもって困難な開墾作業にあたり、さらに役所の手続き、農作物の種子肥料・牛馬豚の買い付け、小作人集めなどに東奔西走した苦闘の生涯は、今日のあらゆる十勝産業の基盤整備の「礎」と高く評価されています。
補足資料
伊能忠敬(1745~1818)は、1800年(寛政12)56才のときの蝦夷地測量から72才まで、10回に及ぶ日本全国の測量をして、有名な「大日本沿海興地全図」完成(没後1821)しています。
間宮林蔵(1775~1844)は、伊能忠敬に測量を学び、西蝦夷地、択捉島、松田伝十郎に従って樺太を探索、1809年(文化6)には単身海峡「間宮海峡」(タタール海峡)を渡り樺太が島であることを確認したといわれます。
松浦武四郎(1818~1888)は、1844年蝦夷地探検に出発。その探査は北海道各地、択捉島や樺太にまで及び、1855年「東西蝦夷山川地理取調図」を出版しています。後に1869年開拓判官となり、蝦夷地を「北海道」と命名、アイヌ語の地名をもとに北海道各地の国名・郡名を選定しています。
|
<参考文献及び参考資料>
・「十勝開拓史」 萩原實編 名著出版 ・「帯広市史」 帯広市 ・「依田勉三の生涯」 松山善三著 ・「北海道の歴史」 榎本守恵著 北海道新聞社 ・「星霜2 北海道史明治2 1875-1985」 北海道新聞社 ・「ほっかいどう百年物語」 STVラジオ編 中西出版 ・「明治の群像 8 開拓と探検」高倉新一郎編 三一書房 ・「北海道の歴史散歩」 北海道高等学校日本史教育研究会編 山川出版社 ・「風吹け、波立て」松本晴雄著 ・映画「新しい風-若き日の依田勉三-」(平成15年)松竹映画DVD ・その他インターネット資料など
*依田勉三の出身地静岡県松崎町の歴史研究家松本晴雄氏より貴重な諸種の資料提供・ご教示を頂きました。
|
依田勉三を記念するもの
■「途別水田の碑」・「徳源地」の碑
依田勉三が北限の水稲の試作を重ね、明治33年(1900)にスタートさせた「晩成舎途別農場」(現在の幕別町依田地区)。苦労の末黒毛品種の栽培に成功して大正9年(1920)11月、この地で祝宴を開いています。この碑は大正9年(1920)9月晩成社によって建てられたもの。この地を「徳源地」と命名しています。兄依田佐ニ平の撰文で、道北地区に元禄時代に入植した伝長坊の努力、その師佐藤信景のことを述べ、晩成社の勉三が長年苦労の末稲作成功の今日を迎えた功績を讃えている。(碑文は漢文表記)
■依田勉三の銅像
晩成社所有地跡、現在は帯広神社前中島公園に立てられています。帯広出身の歌手中島みゆきの祖父中島武市が土地と銅像建立の費用すべてを負担して完成させたもの。彫塑者田嶼碩朗(たじませきろう)は北大のクラーク胸像の制作者でもあります。完成除幕式は昭和16年(1941)6月22日。しかし太平洋戦争中金属献納で供出、現在のものは昭和26年(1951)7月に再建されたものです。
(碑文)<撰文は初代北大総長 佐藤昌介>
功業不磨
依田勉三君ハ伊豆ノ人、夙(つと)ニ北海道開墾ノ志アリ、明治十五年晩成社ヲ組織シ自ラ一族
ヲ率ヰテ此地ニ移住ス、凶歳相次キ飢寒身ニ迫ルト雖モ肯テ屈撓セス移民ヲ慰撫激励シテ原野ノ開拓ニ努メ東ニ水田ヲ開キ、酪農事業ヲ興シ諸種ノ製造工業ヲ試ムル等十勝開発ノ翹楚トシ
テ克ク其ノ範ヲ示ス十勝国ノ今日在ルハ君ノ先見努力ノ賜ナリ岐阜県人中島武市、此ノ労効ヲ
欽仰シ、私財ヲ投シテ之ヲ永遠ニ讃ヘントス誠ニ宜ナリト言フヘシ
■「北海道開拓神社」37番目の祭神となる
北海道神宮境内の「開拓神社」は、昭和13年(1937)8月14日、本道開拓に貢献した36柱の祭
神を祀るため建立されました。戦後になって札幌市議会議長福島利雄、三原武彦(写真家鈴木真一の孫)などが中心になって十勝開拓の祖、依田勉三の合祀運動を起こして、昭和29年(1954)9月22日、37柱目の祭神として合祀されました。
■「依田勉三翁頌徳之碑」(幕別町依田地区)
十勝開拓の先駆者依田勉三の功労を讃えて、「十勝晩成会」が十勝開田の地である依田部落、「徳源地」に、昭和59年(1984)11月に建設したもの。(碑文) <撰文は十勝晩成会副会長 棚瀬善一>
頌徳之碑の由来
十勝開拓の先駆者、依田勉三翁は嘉永六年五月十五日、伊豆国那賀郡大沢村に生れ、大正十四年十二月十二日帯広町西ニ条十丁目の自邸で逝去された。享年七十三才である。
依田家は伊豆屈指の旧家豪農で祖先は甲斐の武田氏に仕えた武家であったが、のち伊豆国那賀郡に帰農した。翁は幼少より漢学者土屋宗三郎の三餘塾に学びまた旧会津藩家老保科正悳の謹申学舎で教をうけた。長じてワッデル塾に入り語学を修めこの時後に晩成社幹部となった。
鈴木銃太郎、渡辺勝の両氏と交わりを深めた。上京して慶応義塾に学び、福沢諭吉先生の薫陶をうけ、さらにその頃伊豆地方は二宮尊徳翁の農本思想の影響がありその感化をうけ、開拓報国の雄志を抱くようになった。明治十四年、北海道開発の宿志を家人に語り同意を得て単身本道開拓地を探査した。翌十五年一族で晩成社を組織し副社長となり、鈴木銃太郎氏と再度渡道し十勝川をさかのぼり、原始境であった帯広を開拓地と定めた。明治十六年翁は渡辺勝氏と開拓団一行を率いて入地し筆舌につくせぬ苦難な開墾が始められた。以来半世紀近く翁は絶望を知らぬ志をもって失敗を重ねつつも次々と事業をおこし、今日十勝におけるあらゆる産業の源流ともいえる事業に心血を注いだのである。
このたび多年の念願であった翁の功績を顕彰感謝するとともにまた十勝開拓につくされた幾多の先覚者の功労にもおもいをいたしここに頌徳之碑を由緒深き徳原地に建設のはこびとなった。
翁の十勝開田の地である依田部落、徳原地組合十勝晩成会幕別町と相計り協讃の方々の賛同を得て建設したことを記す次第である。 昭和五十九年十一月ニ十三日
■晩成社史跡(大樹町生花(おいかま)苗(ない))
十勝開拓の祖と呼ばれる依田勉三がこの地に牧場を開いたのは明治19年(1886)。復元された住居や句碑があります。「依田勉三翁住居」は、明治26年(1893)~大正4年(1915)まで勉三が住んでいた住居で、平成元年(1989)10月に復元されたもの。また勉三が食料不足のため牛20頭を死なせた供養の「祭牛之霊碑」や勉三の「 ふみまなぶ 学び子らが うえおきし 園生のもみじ にほひそめけり」と詠んだ「もみじひら 」の歌碑、サイロ跡などがある。
■「帯広発祥の地」の碑
帯広川の河畔、現在の国道38号線と南6丁目線が交差するあたりに建っています。勉三の「開拓の始めは豚とひとつ鍋」の歌も刻まれています。
■昭和53年(1978)5月、帯広市と静岡県松崎町、「開拓姉妹都市提携」を結ぶ。
■映画「新しい風ー若き日の依田勉三ー」(松竹映画配給)
平成15年(2003)作成。帯広開基120年記念。第38回ヒューストン国際映画祭グランプリ受賞。
■十勝開拓の祖 依田勉三に因む「六花亭」(本社帯広)のお菓子
①「マルセイバターサンド」 北海道産のバターを主原料に、レーズンとホワイトチョコレートを合わせたビスケットでサンド。菓名は、明治30年代に十勝開拓の祖、依田勉三翁経営の牧場で作られたバターのラベル(包装紙複製)に因んでいます。
②「ひとつ鍋」 菓名は、依田勉三翁が開拓当時によんだ句「開墾の はじめは豚と ひとつ鍋」に因み、お鍋をかたどった最中に餡と小さなお餅2個を入れたものです。
③「十三戸」 明治16年、帯広開拓のために依田勉三を団長とする晩成社移民団が入植した13世帯27名に因む。初雪の舞うわらぶきの民家をイメージしたもの。
④「万作」 バター、ミルク、卵を加えた桃山。開拓当時、春一番に咲く福寿草は「まず咲く」がなまって「万作」と呼ばれました。これは、依田勉三の「万作や 何処から鍬を おろそうか」の句に因んだもの。
|
<NO,54>(2008,7,26発行)
北海道庁が招聘した北欧の外人模範農家
ー札幌真駒内種畜場のモーテン・ラーセンと札幌琴似村農事試験場のエミール・フェンガー
十勝地区甜菜農家のフリードリッヒ・コッホ(十勝清水)とウィルヘルム・グラバウ(帯広)―
明治2年(1869)7月、明治政府の開拓使設置により、北海道の本格的な開拓がスタートしますが、明治3年(1870)5月、開拓次官となった黒田清隆は、北海道の開拓や農業経営の模範を米国に求めて、マサチューセッツ州出身の米国農務長官ホーレス・ケプロン(1804-1885)やオハイオ州で牧場経営をしていたエドウィン・ダン(1848-1931)などを招聘したのでした。そして、各地に開拓団が入植して農業開拓がすすめられました。
しかし、北海道農業は、新しい肥沃な原野の開墾地での、無肥料連作を長年続けたために、大正時代に入って次第に地力が落ちてきたといわれます。大正6年(1917)、道庁農政担当者と札幌酪農組合畜牛研究会とが中心になって地力回復のための有畜農業の検討をはじめ、「北海道第2期拓殖計画」として、北欧の有畜農法を北海道農業経営の参考として取り入れることになります。米国留学の酪農家の宇都宮仙太郎(1866~1940)、黒澤酉蔵(1885~1982、酪農学園大学・現とわの森三愛高校の創立者)らの進言もあり、北海道庁(第16代長官、宮尾舜治)も主穀農業から主畜農業に転じたデンマークの大成功に注目していました。
大正11年(1922)から長期派遣で、道庁担当職員の山田勝伴・相原金治・神田不二夫と音江(現深川市)酪農組合長深沢吉平の4名の産業調査員がデンマークに派遣されていた間に、デンマーク模範農家招聘という道の方針が出て、その人選が進められることになりました。大正12年(1923)、北海道庁は、デンマーク人農家2戸、ドイツ人農家2戸を5ヵ年契約で招聘し、札幌近郊と十勝地区で模範経営を行わせることとしました。デンマークでは165名の応募者、ドイツでは8名の候補者の中から、4戸を決定。十五町歩農家としてデンマークのモーテン・ラーセン<33歳・4人家族>(札幌真駒内種畜場内耕地)、五町歩農家としてエミール・フェンガー<31歳・4人家族>(札幌琴似村農事試験場内耕地)、十町歩農家としてドイツのフリードリッヒ・コッホ<43歳・6人家族>(十勝清水)とウイルヘルム・グラバウ<30歳・4人家族>(帯広)の4家族が招かれることになりました。
真駒内種畜場の有畜農業十五町歩農家のモーテン・ラーセン
モーテン・ラーセン(1890~?)は、18歳から20歳までの間、商船学校に学び世界各国の見聞を広め、英語にもドイツ語にも通じていたといわれます。1916年、北シューランドに大農場を購入して多年苦心の結果、その経営に成功し、養鶏事業にも成功していました。
大正12年(1923)7月10日、モーテン・ラーセン(33歳)は、妻リーモア(32歳)、長男ポール(8歳)、長女エテッド(6歳)の4人家族で助手のペダー・スヨンナゴー(25歳)と一緒に、デンマークを出発、ドイツハンブルク港より東亜汽船「アフリカ丸」で出帆して、大震災の影響が残る横浜を避けて、9月12日神戸港に入港、そして9月19日に真駒内種畜場に到着しています。
ラーセン一家は、種畜場の敷地内に北欧風の白い木造家屋を建て、畜舎を作り、農耕馬2頭、乳牛6頭、豚20頭、鶏50羽を飼い、プラオ、カルチベ-ター、ハロー、へーレーキ、播種機、種子選別機などの機械を使って十五町歩の有畜混合農業を経営したといいます。この経営状況は真駒内の農家のモデルとなり、農事や家畜改善に大いに役立ったのでした。北海道大学でもそれまでの主穀農業とモーテン・ラーセンの主蓄農業の違いを克明に記録しました。モーテン・ラーセンは働き者で、家族は4人。いつも大きなエプロンを掛けて太って体格の良い奥さんは親しみやすく、助手のスヨンナゴーも温厚質朴な青年であったといわれています。ラーセンは毎日、家畜の世話や農作業をし、スヨンナゴーも助手としてよく働いたそうです。夫人は午前10時ころと午後にも畑へお茶やおやつを持って行ったようです。夕食後は、一家5人で場内を散歩する日課であったようです。労働と余暇のけじめがはっきりしていて、日曜日は安息日として必ず仕事を休み、2頭の馬にラーセンと妻リーモアがそれぞれ子供を一人ずつ乗せて、円山や琴似の方まで出かけたりしたということです。
近所の人たちは菜園や果樹園の作り方、農機具の使い方などを教わり、野菜や果物の種子をもらって自宅の畑に植え育てるなどの交流があったようです。こうして日本人に親しまれ、有畜農業による地力回復に成果をあげたモーテン・ラーセン一家ですが、5ヵ年の契約を少し残して、昭和2年(1927)11月末札幌を離れ、シベリヤ経由でデンマークへ帰りました。帰国後、酪農業をつづけていましたが、養鶏業の失敗などもあってか、カナダへ移住(1945?)したようで、モーテン・ラーセンの晩年についてはよくわかっていないようです。
また、助手のスヨンナゴー(1900~1963)は、帰国後ユトランド北部で酪農業を経営して、日本語ができることもあって、日本からの多くの研修生を受け入れるなど親日的で
あったそうです。野喜一郎、太田正治(八雲町)、黒澤酉蔵、
佐藤貢なども訪問しています。
その後真駒内地区は大きくかわり、現在は、「真駒内五輪記念公園」(緑町3丁目)の一角にある「ラーセン農場跡」の標識がわずかに往時を偲ばせています。
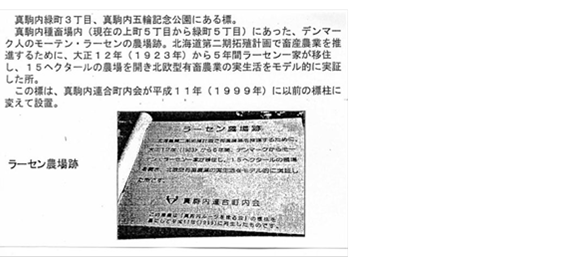
さて、ラーセンやフェンガーが滞在中の大正13年(1924)2月18日から1週間、北海道会議事堂で、一般農民を対象にした「デンマーク農業講演会」(北海道畜牛研究会主催)が開催された時には、二人も講師を依頼されて講演をしています。モーテン・ラーセンは、当時のデンマーク農業の協同組合による成功について話し、エミール・フェンガーは、収穫後の畑作について話しています。また、デンマーク農家の料理法の講習会なども開催されています。
モーテン・ラーセンの農場には、真駒内の北海道種畜場ということもあって、日本人の農業実習生もいました。その中で後に青年酪農家三澤正男氏(1904~1954)(後に道会議員となり、昭和29年9月15号台風の洞爺丸事故により急死。)は、ラーセン家と交遊のあったフリードリッヒ・コッホの次女ヘルタと結婚しています。一男四女があり、現在、長男三澤道男氏(道会議員を務めた)は八雲町で酪農業を経営し、十勝清水でコッホが作ったパン焼き釜を家族で八雲町に移設し、日々使用して大切に保存しているということです。みなさんご家族健在とのことです。三澤家とドイツのコッホ家の親族は今も交流が続いているそうです。次女るみいさんは、丸山孝士夫人として千葉県佐倉市に在住。2001年には、機会を得て、ご家族でドイツのコッホの故郷を訪問した折、日本甜菜糖株式会社札幌支社のお世話により、フリードリッヒ・コッホが勤めていたクラインワンツレーベンの製糖会社も訪問して、日の丸の旗を掲げて歓迎してくれたことに感激を新たにされたそうです。このようにドイツのコッホ家とは今も交流が続いているそうです。
北海道農事試験場(琴似村)の主畜農業五町歩農家のエミール・フェンガー
エミール・フエンガーは、明治27年(1894)生まれで、デンマーク最高のコペンハーゲンの国立農業獣医大学を大正7年(1919)に卒業していますが、なおこの間も含めて約7年間各種農場や農業研究所の実地経験も積んでいます。大正11年(1922)からノーズジョランド農業学校で教鞭を執りながら十町歩農場も経営していました。彼は英語もよくし、妻フリーダも1年半のイギリス遊学の経験があり英語をよく話したといわれ、北海道庁の模範農家としての招聘が決まりました。
大正12年(1923)8月14日、エミール・フェンガー(31歳)は、妻フリーダ(34歳)、長男フリッツ(5歳)、長女オウサ(3歳)の家族と一緒にデンマークを出発、ベルギーのアントワープ(アントウエルペン)経由で東亜汽船「チリー丸」に乗り、10月15日神戸入港、そして10月26日札幌琴似村の農事試験場に到着。五町歩の混合農業を経営しました。
北海道庁は、プラオ、ハロー、カルチベーター、馬車(馬橇)などの農機具をデンマークに注文し、また耕馬2頭、乳牛2頭(後に6頭)、豚3頭、鶏25羽なども手配しています。住宅、畜舎及び納屋などはフェンガー自身が設計してデンマーク風に連結したものを建てています。農業経営は、北欧風農機具を駆使した新しいやり方で、作物は主として飼料用の牧草、根菜、麦類、馬鈴薯、家畜ビートなどであったようです。普通の日課としては、例えば、朝、搾乳後、牧草地に牛を放牧して、畜舎を掃除したり、正午には、畜舎に入れて手入れをして休養させてから再び放牧し、夕刻畜舎に入れて搾乳を行うなどといった生活であったようです。フェンガーは、デンマーク農業参事会にも定期的に詳細な報告を書き送っています。フェンガーは、5ヵ年の契約が満了となり、昭和3年(1928)6月1日札幌を発ちましたが、その当日の出発数時間前まで、琴似の農事試験場での実地指導にあたるという熱心な人であったといわれます。約6ヵ月にわたり、アメリカ・カナダを視察後帰国。ノーズジョランド農業学校教師に復帰しています。
現在、札幌の琴似地区は大きく変り、フェンガーの「農事試験場」を記念するものはなにもなく、後の「北海道農事試験場」も、琴似発寒川沿いに「農試公園」<運動公園>として、わずかにその名残をとどめているにすぎません。

[ 札幌市西区の農事試験場跡ー現在の農試公園(運動公園)]
さて、エミール・フェンガーはその後、コリンズ農業会理事(1930~32)、小作経営(1932~35)、ライングビー農業学校教師(1931~41)、そしてノーズジョランド農業会教師のかたわら農業経営(1945~50)にあたっていましたが、昭和26年(1951)3月、フェンガー57歳の時に、日本政府農林省の招きで、4ヵ年契約で再び妻フリーダとともに来日しています。山形県新庄市の東北農業試験所(平成のフェンガー記念館)所属で、日本各地の講演や農場視察などでデンマーク農法の指導にあたっています。昭和29年(1954)9月、日本の酪農経営の発展に多大な功績を残して、契約満了で帰国しています。なお、昭和43年(1968)エミール・フェンガー氏寄贈の基金による「エミール・フェンガー賞」が設けられています。平成16年(2004)には、農業試験所(住宅・畜舎)は、「フェンガー記念館」として改修、資料なども保存されています。
甜菜(ビート)作付を中心とした十勝地区の十町歩農家・・・コッホとグラバウ
製糖原料であるビート栽培の歴史は古く、北海道では明治初年開拓使の札幌官園での試作に始まりますが、ビート製糖業は、有珠郡西紋鼈(にしもんべつ)の官営紋鼈製糖所
(明13)・晩成社依田勉三の「当縁農場」の甜菜工場などの努力も試作に止まり、その後、「北海道製糖工場」(大8)や「日本甜菜製糖清水工場」(大9)の進出によるビートの作付け指導から本格的な栽培が始まりました。しかし、ビートは連作がきかず、多肥を必要とすることもあり大規模な作付は困難でした。
そこで,道庁は、ビート農家の栽培技術の向上を目指して、甜菜作付を条件とする十勝の十町歩模範農家として、ドイツからフリードリッヒ・コッホとウィルヘルム・グラバウの二農家を招くこととしました。人件費以外の土地、住宅、家畜、畜舎、農業機械等の設備は、「北海道製糖株式会社」(大正8年・1919年設立、大正9年・1920年12月操業開始、現存するビート製糖工場としてわが国最古のもの)と明治製糖株式会社によって無償で提供されて、その他の費用(人件費等)は道庁が支出しています。人選については、ドイツのクラインワンツレーベンン甜菜会社の推薦によってこの2農家の招聘が決まり、大正12年6月に5ヵ年契約の仮契約をしています。

十勝清水滞在当時のコッホの家族写真]
<後列左から>
妻 ベルタ・コッホ 長女 エルナ・コッホ 次女 ヘルタ・コッホ フリードリッヒ・コッホ
<前列左から>
次男 リヒャルト・コッホ 長男 オットー・コッホ
コ ッホの家族写真2枚は丸山るみい氏提供:上と下

コッホ滞在当時の住宅と家族の写真 (下の写真と同じ家)

現在も使用されているコッホの住宅(2008年6月18日撮影)
<写真提供ー清水町教育委員会社会教育係長 安ケ平宗重氏>


大正12年(1923)7月20日、コッホとグラバウの両家族一行10名は、北ドイツのロイド汽船「ウェザー号」で、ブレーメン港を出帆して、9月25日神戸に入港しています。そして、グラバウ家 族は10月3日北海道製糖株式会社所有地(帯広)に、コッホ家族は10月4日明治製糖所牛機会社有地(十勝清水)にそれぞれ現地到着しています。2人とも十勝国において十町歩の甜菜栽培を主とした混合農業経営にあたります。両家族には、ドイツ式のプラオ、ハロー、耕作機、除草機、播種機、ローラー、刈取機、四輪馬車など、さらに耕馬2頭、乳牛3~4頭、豚3~5、鶏35羽などが提供されています。
フリードリッヒ・コッホ(43歳)は、妻ベルタ(43歳)、長男オットー(20歳)、次男リヒャルト(18歳)、長女エルナ(16歳)、次女ヘルタ(15歳)の6人家族。コッホは小学校卒業後、ノラベッツエーク・ウント・ケゼック製糖会社の甜菜部に勤務して、ビート栽培技術者として会社でも高い評価を得ていました。(第一次世界大戦従軍、言語はドイツ語のみ)
コッホと息子2人の3人が主として甜菜の農業経営にあたり、輪作携帯の技術指導をしました。妻と娘2人は家事の処理を担当したようです。住宅・畜舎は、ドイツ農家の設計図を参考にして建てられた2階建(24坪)の立派なものでした。また、畜舎は40坪(7舎)、豚舎5坪、倉庫も40坪という広さでした。
コッホは、十勝での農業経営に情熱と誇りを持ってあたり、その営農の独創性は地元の農民にも大きな影響を与えたといわれます。またコッホは、北海道十勝の生活になじんで、契約期限を2ヵ年延長して、結局、十勝清水に8年いたそうで、その住宅は、現在も保存されているそうです。
昭和5年(1930)11月、札幌で行われた青年酪農家三澤正男氏と次女ヘルタの結婚式を家族全員で見届けて、同年(1930)12月2日、正男・ヘルタに見送られて、家族とともに横浜から帰国しました。
ウィルヘルム・グラバウ(30歳)は、妻マリヤ(35歳)、長男ウイルヘルム(7歳)、長女シャルッティ(5歳)の4人家族。グラバウも小学校卒業後、同じ製糖会社に入社。甜菜の耕作に従事していました。(第一次世界大戦従軍、言語はドイツ語のみ)
グラバウ一家の住宅は、2階建で21坪あり、畜舎・納舎は78坪(6舎)、他に豚舎及び農機具置場15坪という大きな立派なものが提供されています。グラバウは、製糖工場の工員出身で、その営農技術はさほどではなかったようですが、農民であることに強い誇りを持っていた点で、卑屈になりがちな農民に好刺激を与えたといわれます。グラバウは、昭和3年(1928)秋に帰国しています。
作物は、コッホの場合もグラバウの場合もともに、やはり甜菜作付中心とする「混同農業経営」で、他に家畜ビート、家畜人参、燕麦、麦類、トウモロコシ、豆類、馬鈴薯、クローバーなどを栽培していたようです。
その後のコッホ家と三澤家の交流の思い出 (千葉県佐倉市在住 丸山るみい氏 談)
私どもの両親(三澤正男・ヘルタ)は、「昭和5年に、帰国するコッホの家族を横浜港まで見送りに行ったのが私たちの新婚旅行だった」と言っておりました。そして第二次大戦、戦後の東西ドイツの分断、フリードリッヒ・コッホの死、東ドイツとなったコッホの家族とは文通さえも困難な状態が続きましたが、昭和28年(1953)、デンマーク・コペンハーゲンで開催された世界酪農会議に父三澤正男が日本代表団の一員として出席することとなり、それまでかなわなかった母ヘルタの里帰りを期して、二人揃って出かけました。しかし、東ドイツとなった故郷の土を踏むことはできず、ベルリンでの限られた48時間の再会となりました。すでに他界していたフリードリッヒ・コッホを除き、母親ベルタをはじめ12人の家族全員との23年ぶりの再会でした。今は亡き父がこの感激的な再会の様子を何度も何度も話してくれましたのも、懐かしい思い出です。その翌年、昭和29年(1954)9月の洞爺丸台風の事故で、洞爺丸に乗船していた父を私どもは失いました。
故郷をこの目で見たい、その土を踏みたいと思い続ける母ヘルタの里帰りを願う三澤家に、幸いにもその機会が訪れます。昭和58年(1983)11月、当時北海道ホルスタイン農業協同組合の理事・組合長をしていた三澤道男は、ドイツホルスタイン協会及びドイツ人工受精所の招きで、母ヘルタ同伴で訪独。その際、ドイツ側での、ヘルタの故郷訪問実現の努力にもかかわらず、またも、東独にあった故郷への里帰りはかないません
でした。夫の死、かなわぬ再度の里帰り、失意に沈んだ母へルタはその後多くを語ることはありませんでした。でも私の記憶にある両親は、いつもフリードリッヒ・コッホが北海道で果たした業績を誇りとしていたことを知っております。
|
<参考文献及び参考資料>
・外人農家概況 (第一次・大13、4) (第一次訂正増補版・大14、10) (第一次訂正版三版・昭2、7)
(第二次・昭2、8) 北海道庁産業部作成 (道立文書館所蔵)
・外人農家の農業経営法(昭和3、7) 北海道庁産業部作成 (道立文書館所蔵)
・札幌市総務局行政部 文化資料室 郷土史相談室資料 (今倉 迪夫氏提供)
・「清水町史」(コッホについて) ・「大正村史」(グラバウについて)
・郷土研究誌「らんぷ」第3号 ・「帯広市史」昭和59年版
・「写真集ふるさとの思い出11・帯広」 国書刊行会
・帯広百年記念館資料 (学芸研究員 作間 勝彦氏提供)
・復刻版「北海道に於ける独逸人経営の模範農家」(吉村真雄)<「農業世界」昭和3年新年号・2月号>
・論文「大正時代北海道のデンマーク模範農家招聘について」 (北海道東海大学助教授 佐保 吉一氏)
・「真駒内物語」(谷代 久惠著) 北海道新聞社刊
・千葉県佐倉市在住 丸山 るみい氏(フリードリッヒ・コッホの孫娘)から、いろいろ資料・写真提供とご教示をいただきました。近年、丸山るみい氏にドイツの著者から寄贈された次の研究文献があるそうです。『前世紀初頭におけるクラインワンツレーベン製糖工場による甜菜栽培の日本での進展』(原題省略)(エルハルト・ユンクハンス著)=内容はコッホ及びグラバウの日本における甜菜栽培の指導の開始から離日に至るまでの詳細な記録・写真=(丸山るみい氏所蔵)
・その他インターネット資料など
|
ページのトップへ戻る
前のページへ | 次のページへ
ホームへ
|